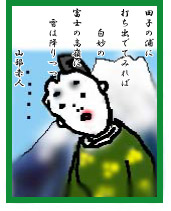『黒木陽子の百人一首を斬る!』
(略して『陽子の百人斬り!』)
【第四回】
田子の浦に 打出て見れば 白妙の
富士の高嶺に 雪は降りつつ
[山部赤人]
●読み
(たごのうらに うちいでてみれば しろたえの
ふじのたかねに ゆきはふりつつ)
●意味
田子の浦の海岸に出てみると、富士の高嶺に真っ白に雪が降り積もっているよ。
ここで事実関係を。
作者:山部赤人(奈良県民。盆地育ち。東国に派遣されて、実際に富士山を目撃)
編者:藤原定家(京都府民。盆地育ち。富士山には・・・あれ?どうなんやろう。行ってないんちゃうかな、多分。(全然事実関係やないやん。推測やん。))
ちなみに、万葉集に載っている原曲は、
「田子の浦ゆうちい出て見れば真白にぞふじの高嶺に雪は降りける」でして、
これじゃちょっと受けが悪いかも、と思ったのかどうかは知らないが、明らかに定家がちょっとアレンジしたのを百人一首に載せているわけです。
さて本題。
いきなりですが、京都は盆地です。
北西東を山に囲まれてまして、現在でも建物が低かったりするので、まっすぐな通りを自転車でこいでいる時など、遠近法の消失点に山が見えます。神戸海沿い育ちの私には、この京都の「箱庭/盆地感」が、いまいましくもあったりします。
そして、この歌は、その「箱庭/盆地感」がポイントになっていると見た。
都の大路を北向きに歩いていて、ふっと視線を上に上げると、京都の低い山々が見えます。その右斜め上は空です。その空白に、赤人が歌った、めっちゃ高いという噂の富士山を思い描いてみるのです。
実際に、京都に住んでいる方はやってみてください。
「えーと、まっすぐな道の先に立って、北を向いて・・・
ああ、確かに山が見えるわあ。
で。斜め上は・・・確かに、空白やね。」
ハイッ!そこでストップ!
そのとき、姿勢はどうなっていますか?
多分、ちょっと上向きに小首をかしげて、アンニュイなポーズになっているはずです。
そう!
この歌は、そんなポーズで読むのが正解なのです!
「振りつつゥ・・・」
最後の母音の「ウ」の口の形が、そのまま、ありもしない空白の富士山へ向かって吸い込まれて行くイメージがつかめたら本物です。
動線を含めて、脳内上演してみましょう。
田子の浦に 打ち出でて見れば
《東西の通りから、十字路を曲がり、南北の通りへ》
白妙の
《目線を右斜め上にうつし、白いものを見る。雲でもいい。》
富士の高嶺に
《さらに、目線を高いところに持って行く》
雪は振りつつゥ
《「ウ」の形の口が、視線の先に届くイメージを持って発音する。》
《感極まって、ひとすじ、涙を流す。》
♪BGM:民俗調のさみしげな響きのある、広がりがあるオーケストラが流れる
拍手!
完璧!すばらしい!
さて、ここで万葉集に戻ってみましょう。
「真白にぞ! ふじの高嶺に雪は振りける!」
いや〜ん。武骨ぅ。
ダメ!ダメダメよ!
変えちゃうわ!
ね。
この歌は、そんな風に読んで下さい。
京都にお出かけの際は、実際にやってみて下さい。
そして、もし、私がその現場に通りかかってしまったら
見て見ぬ振りして、あとで笑います。
さて次回は・・・
【第五番:奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の・・・】
猿丸トンネルでお馴染み・・・と思ったら、トンネルになっているのは蝉丸だった。まったくなんの感慨も思い入れも浮かばないこの歌。次回は大変だな・・・。
(現代語訳は、中央図書「古典の学習【小倉百人一首】」宗政五十緒著」から引用しました。
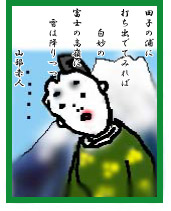
|