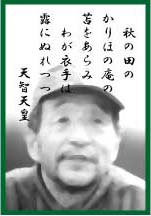【第一回】
秋の田のかりほの庵の苫をあらみ わが衣手は露にぬれつつ [天智天皇]
●読み(あきのたのかりおのいおのとまをあらみわがころもではつゆにぬれつつ)
●意味: 秋の稲田のほとりの仮小屋で番をしていると、その屋根にふいた苫の編み目が荒いので、私の袖は夜露にしきりにぬれることだ。
「蒸し米炊いた大化の改新(645年)」でおなじみの、中大兄皇子。
その彼は、大化の改新後、23年たってようやく天皇に即位。天智天皇となる。
23年と一口にいっても、当時の23年は長い。長いよ。(今も長いけど)
平均寿命がたぶん30そこそこの当時に、なぜ23年も最高権力者にならなかったのか。
自分の名声が下がるのを恐れたのか。
はてさて、当時の天皇は現在の会長職のようなものだったのか。
・・・そんなことはまぁ、さておき(おくのかよ!)
この一首をひとつのセリフとして考察したときに、どこに注目するか、ですが。
ズバッッと・・・
「かりほの庵」(仮庵の庵)
この部分です!!
「かりほぉのいほぉッ・・・」
と、「ほぉ」を2回言うことで、
この歌独特のリズムを生み出しているのダッ!
(正しい発音は、「お」と、書いてありますが、
ここは是非「ホ」に近い「お」と発音したい。)
そして、この発音をいい味出して言えるのは、
日本の俳優でただ一人。
そう、ご存じ、
田中邦衛だ!
若い頃は青大将として暴れまくり、番長/蘇我氏をたおしたものの、
「俺はそんな器じゃねえや・・・」と、影にまわり、
都会に疲れて、手作りの小屋を建てたりして、
孫に囲まれて遺言を書いたりするのだった。
しかし、晩年「ゴロちゃんじゃないと・・」と、
周囲の暖かい声に戸惑いながら天皇になる・・・。
そんな田中邦衛さんをイメージして、この歌を詠んで下さい。
●イメージ
「秋にさぁ、稲穂が広がる田んぼの中におっ建てた・・・
仮の庵の・・・庵のよぉ、屋根に葺いた苫の編み目が荒くってさぁ
俺の上着の袖が、落ちてきた夜露でぬれるんだよぉ・・・
ぽたぽたーっ…ぽたぽたーっってさぁ・・・」
ね?一気にセリフの行間が埋められた感じ!
これで、この役はもう自分のものだね!
次回は・・・
【第ニ番:春過ぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山】
この歌を詠み解きます!
香具山は、今の奈良県橿原市東部に位置する山だ!
紙もっちんの実家からも見えるよ!
(嘘。本当は見えるかどうか知らない。見える?ねえ、紙もっちん〜。)
(現代語訳等は、旺文社 古語辞典[改訂新版]から引用しました。)
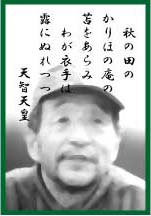
|